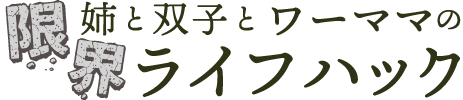こんにちは、ままみです。
長女と双子の男の子、3人の子どもを育てながら働くワーママです。
毎日がドタバタで、思うようにいかないこともたくさん。
それでも「働きたい」「家族との時間も大切にしたい」という気持ちで、試行錯誤しながら続けてきました。
この記事は、私が製造メーカーで唯一テレワーク勤務になった経緯と、そこにたどり着くまでのリアルな体験を書いたものです。
同じように「仕事を続けたいけど、今の働き方では厳しい…」と悩んでいるママの参考になればうれしいです。
目次
全員が「出社前提」の会社
私が勤めているのは、都内に本社・郊外に工場がある中小企業の製造メーカー。
いかにも“出社してなんぼ”な雰囲気の会社です。
名目上の所属は「総務」ですが、実際の仕事はなんでも屋さん。
製品の受注を確認し、プリンターのトナーを交換し、パソコンが動かなくなった社員のデスクに呼ばれ、会社のサイトを更新する。
そんな日常でした。
毎日、片道1時間半の通勤。
出社したらメールチェック、社内の問い合わせ対応、書類作成、来客対応、電話応対。
製造業の「現場を支える」裏方仕事は、地味だけど必要なものばかりです。
第1子の出産と“時短勤務ワーママ”としての復帰
第一子を出産後、保活で苦戦し出産から1年半後に復職しました。
ようやく保育園が決まったときには、ホッとするよりも「戦いが始まる」という感覚の方が強かったです。
先輩ママたちが1時間の時短勤務にしていたので、私も同じように設定。
「みんなそうしてるから」と深く考えずにいました。
でも、わが家は両実家が遠方で、緊急時に預けられる人がいない。
朝は夫に保育園の送りを任せ、子どもが寝ぼけながら朝ごはんを食べているのを横目に、私は先に家を出る。
それでも、電車で1時間半の通勤は体力的にも精神的にもきつい。
ある朝、職場に着いた直後に「熱があるので迎えに来て」と園から電話。
「この3時間って何なんだろう…」と虚無になりながら電車で戻ったこともあります。
保育園からのお迎え要請の電話では、お迎えまで1時間半かかると伝えると、
「1時間半、ですか…どうにかもう少し早く来れませんか?急な高熱なので、何かあるといけないので…」
と、困らせてしまうこともありました。
ぐったりして迎えを待つ子どもの姿が目に浮かび、心臓がキュッ。仕事中のメンバーに頭を下げ、大急ぎで向かいました。
電車が10分遅れたらアウト。ギリギリの毎日
終業時間のチャイムが鳴ると同時にPCをシャットダウン。
コートを片手に駅までダッシュして、電車に飛び乗る。
「お願い、遅延しないで…!」と祈るような気持ちで毎日過ごしていました。
10分の遅延が命取り。
お迎えが間に合わないと、延長料金+保育士さんへのお詫び。
「本当にごめんなさい」と頭を下げながら娘を迎えに行くのが日常でした。
夕飯は簡単に済ませ、寝かしつけたらクタクタ。
洗濯物は干せても畳む余裕はなく、洗濯物の山が常にリビングに鎮座していました。
そんな毎日綱渡りのような生活に、いつまで耐えられるのか分からない不安を抱えていました。
そして双子妊娠。「もう電車に乗れない」と医師の診断
第二子を授かったとき、まさかの双子。喜びと同時に押し寄せたのは「どうしよう」という現実的な不安。
お腹が大きくなるスピードも、体の変化も、第一子のときとは比べものになりません。
満員電車で押されるたびにヒヤヒヤし、次第に出社が難しくなっていきました。
医師からは「出社は身体の負担になるから控えるように」と診断書が。
その紙を片手に、上司に相談しました。
幸い、私の業務の多くはPCで完結する仕事。
上司も理解を示してくれ、会社のノートPCと携帯電話を貸してもらい、在宅勤務を開始することになりました。
当時はコロナ禍で、社内の数人も一時的にテレワークを経験していた時期。
「まぁ今は特別だし仕方ないよね」と、比較的スムーズに受け入れてもらえました。
これが、私のテレワーク人生の最初の一歩です。
双子育児スタート。そしてまた仕事へ
多胎妊娠のため早めに産休に入り、切迫早産の入院を経て出産。
双子育児が始まってからは、昼も夜も区別がない毎日でした。
1人が寝たと思ったらもう1人が泣き、ようやく2人とも寝た頃には夜が明けている。
授乳・おむつ・泣くのローテーションに加えて、保育園に通う長女の生活リズムを崩すわけにはいかない。
何度も「無理かもしれない」と思いました。
「育休でこんな生活なのに、仕事が始まったらどうなるんだろう?」という不安がずっと付きまとっていました。
2時間時短勤務で復職。…でも、現実は厳しかった
復職当初は、2時間の時短勤務に変更してスタート。
それでも保育園の送り迎え・家事・仕事をこなすのは限界ギリギリ。
子どもの体調不良や通院でどんどん減っていく有給休暇。
1年目は繰越しの有休があったのに気づけば使い果たし、年度末には欠勤に。
2年目は、新年度から2ヶ月半で有休ゼロ。
「これはもうやっていけない」と悟りました。
夫も仕事が忙しく、親も遠方。
もう退職するしかない。
覚悟を決めて上司に伝えました。
上司からの提案。「在宅でやってみたら?」
退職の意思を伝えた私に、上司が静かに言いました。
「在宅勤務でやってみたら?ままみさんの仕事ならできるんじゃない?」
まさか、上司のほうからそんな提案があるとは思っていませんでした。
たしかに、私の業務の大半はリモートでもできる。
「会議はオンラインで出席すればいいし、ままみさんなら誰もサボってるなんて思わないよ」
そう言ってくれた上司の言葉に、涙が出そうになりました。
そして、辞める覚悟でいた私は一転、“社内唯一のテレワーク社員”になったのです。
社内の理解と、ほんの少しの罪悪感
もちろん、すべてが順風満帆だったわけではありません。
電話応対や来客対応など、私の代わりに現場で対応してくれる同僚たちには、正直申し訳なさが残ります。
「自分だけ楽をしているんじゃないか」と感じることもありました。
それでも、子育て中の社員も多く、
「今が一番大変な時期だから」と理解を示してくれたことで、少し心が軽くなりました。
在宅勤務になって変わったこと
在宅勤務が始まってから、生活は少しずつ安定しました。
洗濯物の山も、なくなるわけではありませんがエベレストから富士山レベルに。
保育園から「熱があります」と連絡があっても、すぐに迎えに行ける。
朝の業務開始前や昼休み時間に簡単な家事もできる。
対面ですぐに済むことをメッセージや電話でやりとりすることで仕事のペースは落ちましたが、
「無理して通勤するよりはずっといい」と思えるようになりました。
小さな会社だからこそ、融通がきいた
私が働いているのは、いわゆるアットホームな中小企業。
社員も全員お互いを知っているので、別の事業所の社員も「なんか双子で大変らしい」、くらいは知られているみたいです。
正直、私の働き方を他の社員の人たちがどう思っているのかは分からないけど…(中にはよく思っていない人もいるはず)
上司に直接相談できたこと、
ママ社員が複数いたこと、
業務がリモート対応できる内容だったこと。
そのすべてが重なって、今の働き方が実現しました。
いまの気持ちと、これから
正直、いまでも「いつまで続けられるだろう」という不安はあります。
子どもの体調次第で予定が崩れ、PCに向かえない日もある。
そんなときはどうしても「仕事を辞めたら楽になれる?」という妄想をしている自分がいます。
それでも、在宅勤務があったからこそ、“完全に働くことを諦めずに済んでいる”。
もし、あのとき何も言わずに辞めていたら、今の私はいません。
同じように悩むママたちへ
在宅勤務といっても、会社や業種によってできる範囲は違います。
でも共通して言えるのは「一度、相談してみること」。
“辞める前に、伝えてみる”だけで道が開けることがあります。
私の場合、コロナ禍や業務内容など、たくさんの偶然が重なって実現しました。
けれど、どんなに小さな会社でも「人の理解」があれば、働き方は変えられる。
完璧な両立なんてないけれど、
“なんとか回していける方法”は、きっとあるはずです。
まとめ:在宅勤務を実現できた3つのポイント
- 産前にしていた業務が在宅でも可能だった
- ママ社員が複数いて理解が得やすかった
- 上司に直接相談できた関係性があった
今の自分に合った働き方ができるようになったのは、環境や上司、同僚、たくさんの人に恵まれていたから。
けれど、そこに「諦めなかった自分」も確かにいました。
限界を感じても、悩んでも、
「こうなったらいいな」と思う働き方を少しずつ形にしていけたら。
この体験が、今迷っている誰かの背中をそっと押せたらうれしいです。